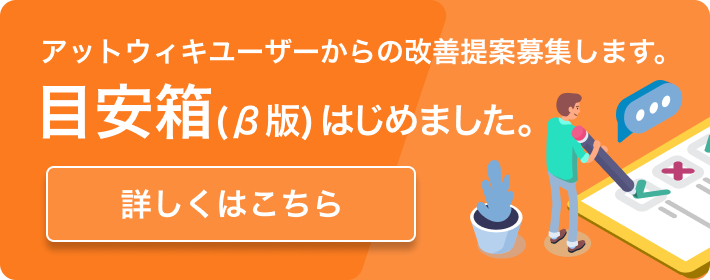第七回
「ながみ藩国へ?」
訪ねたのは、摂政のアシタスナオ(整備士モード)だった。
休憩中だったか、右手には三角のおむすび。おむすびは基本的に三角握り飯なので、
三角のおむすびだと二重表現になるのだが、それはまあどうでもいい
このおむすびは「夢と現と幻亭」のおむすびセットで、
「夢と現と幻亭」とは、整備工場付きのメイド喫茶である。
キノウツン国は整備工場にもメイド喫茶が設備されていた。
余談だが、この店でおにぎりを注文すると、必ずメイドさんが
「おにぎりは暖めますか?」と聞いてくる(キノウツン国の魂の故郷は北海道にある)。
はいと答えるとレンジで温めたおむすびを手渡されるのだが、それは本当にどうでもいい。
ともかく、ここは整備工場だった。
現在のアシタスナオは「キノウツンの誇り」に出撃したI=Dの整備に駆り出されている。
正規軍相手にドンパチやらかした我が藩のI=Dは、
あちこち煤だらけで表面はぼこぼこのフレームはガタガタになっていた。
電気屋なら「買い換えた方が早いですねえ」と言うことだろう。
「ながみ藩国ねえ。って、お前あそこは...」
「あそこは?」
「いや...」おむすびを口に頬張った。咀嚼し、飲み込んでから「なんでまた、ながみ藩国なんだ」
「せっかく、帰郷したんだからあまり遠出したくなくてな。隣国だし、そう長旅にもならないだろ」
「お前さんが見る所なんて、田んぼと沢ぐらいだと思うんだがなあ」
自分のおむすびを見つめ、うなる摂政。
訪ねたのは、摂政のアシタスナオ(整備士モード)だった。
休憩中だったか、右手には三角のおむすび。おむすびは基本的に三角握り飯なので、
三角のおむすびだと二重表現になるのだが、それはまあどうでもいい
このおむすびは「夢と現と幻亭」のおむすびセットで、
「夢と現と幻亭」とは、整備工場付きのメイド喫茶である。
キノウツン国は整備工場にもメイド喫茶が設備されていた。
余談だが、この店でおにぎりを注文すると、必ずメイドさんが
「おにぎりは暖めますか?」と聞いてくる(キノウツン国の魂の故郷は北海道にある)。
はいと答えるとレンジで温めたおむすびを手渡されるのだが、それは本当にどうでもいい。
ともかく、ここは整備工場だった。
現在のアシタスナオは「キノウツンの誇り」に出撃したI=Dの整備に駆り出されている。
正規軍相手にドンパチやらかした我が藩のI=Dは、
あちこち煤だらけで表面はぼこぼこのフレームはガタガタになっていた。
電気屋なら「買い換えた方が早いですねえ」と言うことだろう。
「ながみ藩国ねえ。って、お前あそこは...」
「あそこは?」
「いや...」おむすびを口に頬張った。咀嚼し、飲み込んでから「なんでまた、ながみ藩国なんだ」
「せっかく、帰郷したんだからあまり遠出したくなくてな。隣国だし、そう長旅にもならないだろ」
「お前さんが見る所なんて、田んぼと沢ぐらいだと思うんだがなあ」
自分のおむすびを見つめ、うなる摂政。
農業の国、ながみ藩国。その主生産は稲である。
20t生産できるらしいので作付け面積は4k㎡ぐらいか。
食糧事情が芳しくないキノウツン国は食料の大半を輸入で賄っている。
米もその一つで、いま彼が食べているおにぎりにも、ながみ藩国の米が使われているのかもしれない。
田んぼと(沼)沢しかないと言うが、それで充分だろうとは思う。
麦穂には猫の神が住むという。それを拝観するのも一興だろう。
「農業見学も立派に観光だろうさ。
遺跡とかもあるらしいし、歴史的にも面白い成り立ちの国だから、それを取材してもいい」
ながみ藩国は、原住民が植民者を追い出したと言う歴史を持つ国だった。
「なあ...もう少し待ってから行かないか?」
摂政は、やはり気むずかしい顔だった。
「なんでさ」
「具体的には次のターンぐらいだが」
「? どういうことだよ」
「まあ、いいけど。行きたいなら俺は止めやしねえ。どうせ他に理由があんだろ?」
どん、と胸を叩かれる。
「話が早くて助かるよ」
アシタスナオは残りのおむすびを口につっこんで、スパナを握ってあっちいけと手を振った。
20t生産できるらしいので作付け面積は4k㎡ぐらいか。
食糧事情が芳しくないキノウツン国は食料の大半を輸入で賄っている。
米もその一つで、いま彼が食べているおにぎりにも、ながみ藩国の米が使われているのかもしれない。
田んぼと(沼)沢しかないと言うが、それで充分だろうとは思う。
麦穂には猫の神が住むという。それを拝観するのも一興だろう。
「農業見学も立派に観光だろうさ。
遺跡とかもあるらしいし、歴史的にも面白い成り立ちの国だから、それを取材してもいい」
ながみ藩国は、原住民が植民者を追い出したと言う歴史を持つ国だった。
「なあ...もう少し待ってから行かないか?」
摂政は、やはり気むずかしい顔だった。
「なんでさ」
「具体的には次のターンぐらいだが」
「? どういうことだよ」
「まあ、いいけど。行きたいなら俺は止めやしねえ。どうせ他に理由があんだろ?」
どん、と胸を叩かれる。
「話が早くて助かるよ」
アシタスナオは残りのおむすびを口につっこんで、スパナを握ってあっちいけと手を振った。
『となりの藩国は面白い~ながみ藩国編~』
と、手荒い見送りでやってきたながみ藩国であったが、
「なるほどなぁ」
夕刻少し前。稲のない田んぼでは、子供たちの声が賑やかだ。
手に握ったチラシをボンヤリと見る。
「なるほどなぁ」
夕刻少し前。稲のない田んぼでは、子供たちの声が賑やかだ。
手に握ったチラシをボンヤリと見る。
“金・原油相場追証不要”
と告されたチラシ(入国時に渡された)だった。それを、ぼんやりと眺める。ちなみに、その右には、
“NHKの「仰天エロ日記」に新事実”
と書かれていた。
まあ、それはともかく。
まあ、それはともかく。
ながみ藩国の農業生産地は、そこらじゅう土と藁束の山だった。収穫が終わった後である。
麦穂が波のようにうねる姿を見たくはあったのだが、時期が時期なので仕方がない。
猫の神様に会うのはまた来年である。
湿り気を帯びた空気に土の匂いが混じって鼻腔をくすぐる。
国土の70%が熱帯雨林という話だが、この辺はさほど蒸し暑さもない。
この場所は、過去の入植者によって開墾された農業地という話だった。
座る土手の溝には、毛の生えたカエルがとびはねている。
その向こう、土のむき出した田んぼでは、現地の子供たちがボール遊びをしていた。
ガキ(名前)はと言うと、その子供たちと混じってはしゃいでいる。
異国人同士だというのに、まるで昨日もそこで遊んだかのような馴染みっぷりだ。
ガキが人見知りしないのか、ながみ藩国の子供たちがおおらかなのか、おそらくその両方だろう。
どうやら、ドッヂボールをやっているらしい。ガキのチーム側がボロ負けしていた。
ガキは陣の中でボールも捕らずに逃げ回っていた。
刈り取った稲のデッキブラシの毛先のような跡に足を取られ、何度もこけていた。
麦穂が波のようにうねる姿を見たくはあったのだが、時期が時期なので仕方がない。
猫の神様に会うのはまた来年である。
湿り気を帯びた空気に土の匂いが混じって鼻腔をくすぐる。
国土の70%が熱帯雨林という話だが、この辺はさほど蒸し暑さもない。
この場所は、過去の入植者によって開墾された農業地という話だった。
座る土手の溝には、毛の生えたカエルがとびはねている。
その向こう、土のむき出した田んぼでは、現地の子供たちがボール遊びをしていた。
ガキ(名前)はと言うと、その子供たちと混じってはしゃいでいる。
異国人同士だというのに、まるで昨日もそこで遊んだかのような馴染みっぷりだ。
ガキが人見知りしないのか、ながみ藩国の子供たちがおおらかなのか、おそらくその両方だろう。
どうやら、ドッヂボールをやっているらしい。ガキのチーム側がボロ負けしていた。
ガキは陣の中でボールも捕らずに逃げ回っていた。
刈り取った稲のデッキブラシの毛先のような跡に足を取られ、何度もこけていた。
「あのあほ...誰が洗濯すると思ってるんだ」
土手に座り、真っ黒になったガキを見てぼやく。
砂色の西国人服はすでに泥まみれで、泥の付いていない箇所を探す方が難しい。
引っこ抜いた直後のジャガイモを連想させる。
「いやいや、妹さんはよくやってなさる」
隣でタオルを巻いた爺さんが喜色満面の顔でそう言った。
刈入れ時期だというのに麦わら帽をかぶっている。
「いや娘ですけど」と、訂正してから、「そうですか? 逃げ回ってるだけのような」
「逃げるにしてもボールが味方の外陣に流れるように考えとるよ。
それに、逃げてはいるようだが、怖がっていると言うわけではなさそうだ。
油断しているとやられかねんぞ」
「まさか」
土手に座り、真っ黒になったガキを見てぼやく。
砂色の西国人服はすでに泥まみれで、泥の付いていない箇所を探す方が難しい。
引っこ抜いた直後のジャガイモを連想させる。
「いやいや、妹さんはよくやってなさる」
隣でタオルを巻いた爺さんが喜色満面の顔でそう言った。
刈入れ時期だというのに麦わら帽をかぶっている。
「いや娘ですけど」と、訂正してから、「そうですか? 逃げ回ってるだけのような」
「逃げるにしてもボールが味方の外陣に流れるように考えとるよ。
それに、逃げてはいるようだが、怖がっていると言うわけではなさそうだ。
油断しているとやられかねんぞ」
「まさか」
即座に否定したのが、しかし老人の予言は実際のものとなった。
敵陣の子供がガキに力の抜けたボールを投げた。
その子供にしてみれば、どう避けられるだろうから、外陣へのパスのつもりで投げたのだろう。
ガキはその甘い球を見逃さなかった。足場の緩い田んぼの土を蹴って、
前に出る――キノウツンの猫士は器用ではないが、敏捷が3である。
ガキはその俊足を活かし、甘いボールをあっさりと受け止めて、その勢いで敵前に躍り出た。
まさか反撃されると思っていなかった子供は、その場で棒立ちのままだった。
不敵に笑うガキ。そして、
「って、何でドッヂ描写なんだよ。観光はどうなったんだよ」
白熱するドッヂボールを眺めながら、ぼやく。
「おや、観光客の方だったか」
「はぁ。そうですけど」
本当はもう一つ理由があったのだが、そっちの方は空振りだった。
「そうかそうか。てっきり商い師かと思うとったわ。最近は西国の人の入りが多くてのう」
「ああ。それは...」
聯合ルールのせいだろう。
食料生産地を所有しない西国人にとって、農業国との貿易提携は最重要事項である。
その調査のために各国から調査外交に訪れる西国人が増えたとしても、不思議ではない。
「そういうのは、俺の仕事じゃないんですよ」
苦笑する。
「ふむ、では観光客どの。どうかね、我が国は」
老人がドッヂボールを見ながら、何気なく訪ねた。
「一応あちこち見て回りましたけど。強い国ですね」
同じく見ながら、率直に思ったことを言った。
「はっはっは。強い国か、そりゃあいい」
「食料があって歩兵がいてパイロットがいて医者がいるんです。
これほど軍事バランスが取れた国はないですよ」
akiharu藩国が同じ構成だが...まあ、あの国はなんか違うような気がする。
敵陣の子供がガキに力の抜けたボールを投げた。
その子供にしてみれば、どう避けられるだろうから、外陣へのパスのつもりで投げたのだろう。
ガキはその甘い球を見逃さなかった。足場の緩い田んぼの土を蹴って、
前に出る――キノウツンの猫士は器用ではないが、敏捷が3である。
ガキはその俊足を活かし、甘いボールをあっさりと受け止めて、その勢いで敵前に躍り出た。
まさか反撃されると思っていなかった子供は、その場で棒立ちのままだった。
不敵に笑うガキ。そして、
「って、何でドッヂ描写なんだよ。観光はどうなったんだよ」
白熱するドッヂボールを眺めながら、ぼやく。
「おや、観光客の方だったか」
「はぁ。そうですけど」
本当はもう一つ理由があったのだが、そっちの方は空振りだった。
「そうかそうか。てっきり商い師かと思うとったわ。最近は西国の人の入りが多くてのう」
「ああ。それは...」
聯合ルールのせいだろう。
食料生産地を所有しない西国人にとって、農業国との貿易提携は最重要事項である。
その調査のために各国から調査外交に訪れる西国人が増えたとしても、不思議ではない。
「そういうのは、俺の仕事じゃないんですよ」
苦笑する。
「ふむ、では観光客どの。どうかね、我が国は」
老人がドッヂボールを見ながら、何気なく訪ねた。
「一応あちこち見て回りましたけど。強い国ですね」
同じく見ながら、率直に思ったことを言った。
「はっはっは。強い国か、そりゃあいい」
「食料があって歩兵がいてパイロットがいて医者がいるんです。
これほど軍事バランスが取れた国はないですよ」
akiharu藩国が同じ構成だが...まあ、あの国はなんか違うような気がする。
「なるほどなあ。だが農業を謳う国が言われる言葉ではないわな」
10年前に国として形を持ったというながみ藩国。
1900年前に入植者を追い返した原住民族によるこの国家は、
近代技術の力も借りてどんどんと発展を続けている。
もちろん、農作業も機械化が徐々に進んでいて、
にゃんにゃんでは2位タイの生産力を誇る国にまで上り詰めている。
そう、農業も発展しているのだ。
だが、それ以上に――
「...まあ、それはともかく、あの水車に煙突がついたみたいなの、もう使わないのですか?」
ガキたちを挟んで向こう側の土手。
コンバインの横に、同じぐらいの大きさで細長い木の箱が、でんと立っている。
社会の教科書にでも載ってそうな箱だ。
「唐箕のことかね。脱穀した稲を選別する用具だが」
風を運ぶ力加減が難しいんじゃと、老人はぼやいた。
「そうだな、まだ現役ではあるが、農家によっては機械の選別機に跡目を譲っとるな。
あれも単純な仕組みの割に便利ではあるが、やはり機械には勝てん」
「...それは名残惜しいですね。味があって面白いと思うんですけど、」
木で出来た穀物選別機。自然と機械の間にあるようなそれは、現役というのにひどく昔を思わせる。
近代科学の波に流され、これらが後ろに追いやられるというのは、
観光する者にとっては残念な気持ちにはなる。
使わないのならメイド喫茶のエクステリアに持って帰りたいぐらいだった。
「そうは言うが、お前さん。あのトウミも数年前に急いて拵えたえたものだ。
過去の資料を頼りにしてな。やから、そう古いもんじゃあない。
名残惜しむどころか、わしらにとってはテレビを買い換えるようなもんだ」
「はぁ、そういうもんですか?」
どうも、感傷に浸ってるのは自分だけらしい。
ながみ藩国の人にとっては、トウミもコンバインも一緒の扱いなのだろう。
10年前に国として形を持ったというながみ藩国。
1900年前に入植者を追い返した原住民族によるこの国家は、
近代技術の力も借りてどんどんと発展を続けている。
もちろん、農作業も機械化が徐々に進んでいて、
にゃんにゃんでは2位タイの生産力を誇る国にまで上り詰めている。
そう、農業も発展しているのだ。
だが、それ以上に――
「...まあ、それはともかく、あの水車に煙突がついたみたいなの、もう使わないのですか?」
ガキたちを挟んで向こう側の土手。
コンバインの横に、同じぐらいの大きさで細長い木の箱が、でんと立っている。
社会の教科書にでも載ってそうな箱だ。
「唐箕のことかね。脱穀した稲を選別する用具だが」
風を運ぶ力加減が難しいんじゃと、老人はぼやいた。
「そうだな、まだ現役ではあるが、農家によっては機械の選別機に跡目を譲っとるな。
あれも単純な仕組みの割に便利ではあるが、やはり機械には勝てん」
「...それは名残惜しいですね。味があって面白いと思うんですけど、」
木で出来た穀物選別機。自然と機械の間にあるようなそれは、現役というのにひどく昔を思わせる。
近代科学の波に流され、これらが後ろに追いやられるというのは、
観光する者にとっては残念な気持ちにはなる。
使わないのならメイド喫茶のエクステリアに持って帰りたいぐらいだった。
「そうは言うが、お前さん。あのトウミも数年前に急いて拵えたえたものだ。
過去の資料を頼りにしてな。やから、そう古いもんじゃあない。
名残惜しむどころか、わしらにとってはテレビを買い換えるようなもんだ」
「はぁ、そういうもんですか?」
どうも、感傷に浸ってるのは自分だけらしい。
ながみ藩国の人にとっては、トウミもコンバインも一緒の扱いなのだろう。
自省する自分に、老人は黙り込んで腰を下ろした。
隣に座られると、随分と迫力のある老人だった。
「お前さん、機械ばっかりで内実が伴っておらんと思っておるだろう」
「いや、そんなわけじゃ...」
「っはっは。お前さんが言う強い国とはそう言う事だろう。
稲作が主生産の農業国なのに機械と軍事ばっかりかよ、と。そう思っておるわけだ」
つばを飛ばして笑われる。
「どうだ。ん?」
「...はぁ」
まあ図星だった。
ながみ藩国にやってきた近代化の波は農業だけではなかった。むしろ軍事にこそ著しかった。
特に戦車の開発に代表される戦車兵部門は、最強レベルにまで強化されつつあった。
特に――気づいているのかいないのか、中距離戦闘においては最強国レベルである。
ドーピングをするわけでもないのに、だ。それがどれほどの強さであるというのか。
農業国という側面とは裏腹に、この国は、とてつもなく強くなりつつあった。
摂政が観光を止めたのはこれが理由である。
怖いから行くなという意味ではなく、もう少し農業国の特色が出てから言ってみたらどうだと、
そう言う忠告なのだった。
もっとも、この国、次は戦車を作るらしいが。
「なあに。心配はいらんよ」
しかし、老人は磊落に笑うだけだった。
皺に隠れて細くなった瞳は、ドッヂボールをする子供たちに向けられている。
「わしらはなにも生産だけのために農業をやっているわけじゃない。
この国の者にとって、農作は道楽でもあるんじゃ。
だから一位でなくてもいいし、戦車が増えてもよいのだ。
家に帰れば、田んぼがわしらを待っておる。わしらはみんなそうじゃ」
老人の言うことに嘘偽りはない。この国、国民全員が世襲で農業を営んでいる。
そのため、完全失業率が0%だった。兵士にはみな、帰る田んぼが待っているのだ。
「強くなるのは、生きて帰るため。わしらが戦うのは、わしらの生活を取り戻すためだ。
今も昔もそれは変わらん。
戦って帰ってきて、明日は沼沢の間を耕して稲の世話をする。
そう言う生き方、こういう道楽なのだよ。
どれだけ便利になろうと、強くなろうと、道楽までは変わりはしねえだろうさ」
隣に座られると、随分と迫力のある老人だった。
「お前さん、機械ばっかりで内実が伴っておらんと思っておるだろう」
「いや、そんなわけじゃ...」
「っはっは。お前さんが言う強い国とはそう言う事だろう。
稲作が主生産の農業国なのに機械と軍事ばっかりかよ、と。そう思っておるわけだ」
つばを飛ばして笑われる。
「どうだ。ん?」
「...はぁ」
まあ図星だった。
ながみ藩国にやってきた近代化の波は農業だけではなかった。むしろ軍事にこそ著しかった。
特に戦車の開発に代表される戦車兵部門は、最強レベルにまで強化されつつあった。
特に――気づいているのかいないのか、中距離戦闘においては最強国レベルである。
ドーピングをするわけでもないのに、だ。それがどれほどの強さであるというのか。
農業国という側面とは裏腹に、この国は、とてつもなく強くなりつつあった。
摂政が観光を止めたのはこれが理由である。
怖いから行くなという意味ではなく、もう少し農業国の特色が出てから言ってみたらどうだと、
そう言う忠告なのだった。
もっとも、この国、次は戦車を作るらしいが。
「なあに。心配はいらんよ」
しかし、老人は磊落に笑うだけだった。
皺に隠れて細くなった瞳は、ドッヂボールをする子供たちに向けられている。
「わしらはなにも生産だけのために農業をやっているわけじゃない。
この国の者にとって、農作は道楽でもあるんじゃ。
だから一位でなくてもいいし、戦車が増えてもよいのだ。
家に帰れば、田んぼがわしらを待っておる。わしらはみんなそうじゃ」
老人の言うことに嘘偽りはない。この国、国民全員が世襲で農業を営んでいる。
そのため、完全失業率が0%だった。兵士にはみな、帰る田んぼが待っているのだ。
「強くなるのは、生きて帰るため。わしらが戦うのは、わしらの生活を取り戻すためだ。
今も昔もそれは変わらん。
戦って帰ってきて、明日は沼沢の間を耕して稲の世話をする。
そう言う生き方、こういう道楽なのだよ。
どれだけ便利になろうと、強くなろうと、道楽までは変わりはしねえだろうさ」
「...そう、ですね」
戦争が数値で決まろうと、国は数値では決まらない。
キノウツンは美人の国だ。数値的に外見が上の国などいっぱいいるが、それでも美人の国なのだ。
なぜなら、自分たちがそう自称するからだ。
そして、それをまあいいかと認めてくれる人たちがいるからだ。
内側と実際が違おうとも、農業の国であると言い続けて、
それを認め続ける国があるならば、ながみ藩国は農業国なのだった。
そして、この国の米は美味しい。
「そうですね...そういうものなんでしょうね」
「ああ、そうだろうな」
わっと子供たちの歓声が聞こえた。
「まあ、それはそれとして、うちと聯合して米を分けてもらえると結構ありがたいんですけど」
「そうだなあ。キノウツンが燃料生産地を施設したら藩王も考えなくはないんじゃないか?」
風が涼しいを通り越して冷えてきた。
太陽の位置がいつの間にか低い。
ちょうど、ドッチボールも終わったようだった。
ガキは巻き返しもむなしく敗北したらしい。泥だらけの体で、めちゃくちゃ悔しがっていた。
自分はと言うと、泥まみれで悔しがるガキを見てどう叱ってやろうか、とそんなことを考えていた。
戦争が数値で決まろうと、国は数値では決まらない。
キノウツンは美人の国だ。数値的に外見が上の国などいっぱいいるが、それでも美人の国なのだ。
なぜなら、自分たちがそう自称するからだ。
そして、それをまあいいかと認めてくれる人たちがいるからだ。
内側と実際が違おうとも、農業の国であると言い続けて、
それを認め続ける国があるならば、ながみ藩国は農業国なのだった。
そして、この国の米は美味しい。
「そうですね...そういうものなんでしょうね」
「ああ、そうだろうな」
わっと子供たちの歓声が聞こえた。
「まあ、それはそれとして、うちと聯合して米を分けてもらえると結構ありがたいんですけど」
「そうだなあ。キノウツンが燃料生産地を施設したら藩王も考えなくはないんじゃないか?」
風が涼しいを通り越して冷えてきた。
太陽の位置がいつの間にか低い。
ちょうど、ドッチボールも終わったようだった。
ガキは巻き返しもむなしく敗北したらしい。泥だらけの体で、めちゃくちゃ悔しがっていた。
自分はと言うと、泥まみれで悔しがるガキを見てどう叱ってやろうか、とそんなことを考えていた。